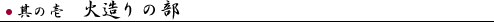
|
| 一、鋼切り |
| 鋼材を薄く伸ばして庖丁の分量に切る。 |
| 二、鋼付け |
| 切り分けた鋼を鉄地金に鍛接材を付けて合わせる。 |
| 三、沸かし付け |
| 炉で八〇〇〜九〇〇度に熱して仮付けをする。 |
| 四、先伸ばし |
| 庖丁の先になる部分を伸ばす。 |
| 五、中子伸ばし |
| 庖丁の柄に差し込む部分、先を尖らせて伸ばす。 |
| 六、総火造り |
| 熱して叩き鍛え、庖丁の形に整える。 |
| 七、焼き鈍 |
| 硬軟むらを防ぐため、鋼をわら灰の中で徐々に除熱し寝かせる。 |
|
 |
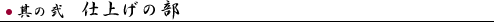 |
| 八、べと取り |
| 火造りで生じた酸化皮膜、酸化鉄を取り除く。 |
| 九、荒叩き |
| 庖丁を叩き締め、分子密度を詰める常温打ち。 |
| 十、裏磨き |
| 鋼を付けた部分、庖丁の表面を研削する。 |
| 十一、地断ち |
| 荒叩きして鋼からはみだした地金を断ち切る。 |
| 十二、本均し |
| 裏面をむらのないように締め打ち、均す。 |
| 十三、刻印打ち |
| 鋼印に彫った名前を打ち込む。 |
| 十四、罫引き |
| 裏面に庖丁型をのせて罫線を引く。 |
| 十五、型断ち |
| 罫線に沿り型断ちをする。 |
| 十六、磨り回し |
| 型断ちされた庖丁の側面を磨る。研削機ややすりで仕上げる。 |
| 十七、前処理 |
| 焼き入れ前に伴う、油気や汚れの除去作業。 |
|

|
 |
| 十八、泥塗り |
| 空気酸化、焼きむら防止のため庖丁前面に塗布。 |
| 十九、焼き入れ |
| 八〇〇度前後に加熱し、水で冷却する。 |
| 二十、焼き戻し |
| 再加熱することにより弾力と強靭性を鋼にもたせる。 |
| 二一、歪打ち |
| 焼入れで生じた狂いを修正する |
|
 |
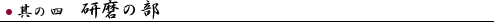 |
| 二二、粗切り刃砥ぎ |
| 表側、切り刃を円砥石で研ぎ下ろす。 |
| 二三、粗平研ぎ |
| 表、表面の研ぎ下ろし。 |
| 二四、粗裏研ぎ |
| 裏側(鋼面)の研ぎ下ろし。 |
| 二五、粗棟研ぎ |
| 大棟から峰(きっさき)にかけての研ぎ下ろし。 |
| 二六、歪取り |
| 研いで歪んだ部分の修正。 |
| 二七、中目研ぎ |
| 粗研ぎより少し細かい砥石で研ぐ。 |
| 二八、羽布磨き |
| 膠(にかわ)で金剛砂を貼り付けた布製の回り砥石で磨く。 |
| 二九、木砥仕上げ |
| 木盤に金剛砂を塗って研ぎ線を出す。 |
| 三十、化粧仕上げ |
切り刃を裏を砥石粉で色出しをする。 |
| 三一、小刃付き仕上げ |
| 刃先を手研ぎ砥石で小刃引き研ぎをする。 |
|
|
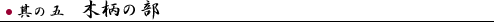 |
| 三二、原木削り |
| 木柄寸法に割って乾燥させたものを柄型に丸く削る。 |
| 三三、際つけ |
| 輪を嵌める部分を削る。 |
| 三四、穴あけ |
| 中子を差し込む穴を錐であけ焼き込む。 |
| 三五、輪はめ |
| 水牛角を輪の寸法に切り、柄の頭に差し込んで固定する。 |
| 三六、磨き |
| 角と朴木柄に磨きをかけ、光沢と手触りの良さを高める。 |
|
|
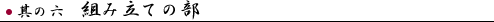 |
| 三七、柄付け |
| 中子を赤めて焼き込み、柄に叩き込む。 |
| 三八、歪みとりと検品 |
| バランスや狂いを修正する。 |
| 三九、防錆処理 |
| 庖丁の錆び止めに防錆剤を塗布する。 |
| 四〇、包装 |
| 箱詰めして包装する。 |
|
|











